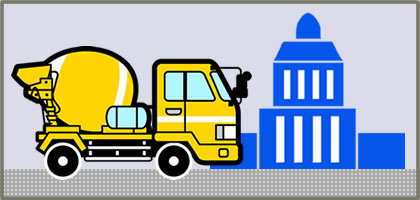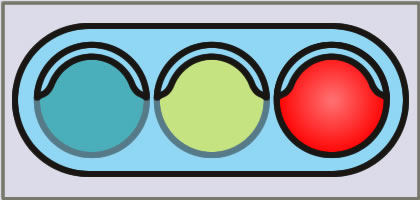戦前の「大阪労働学校」のゆかりの地を探索する(11)

著:本山義彦(大阪労働学校・アソシエ 学長)
●労働組合の存続とストライキ●
第二次世界大戦後の「憲法」二八条に明記されるまでは、「労働三権」という権利は、「実質的」には認められていなかった(「法的」にはあいまいな表現で認められてはいた。「治安維持法」も然り)。法とは、「明確な文言」によって「厳密に表現」されないかぎり、いくらでも権力側によって「恣意的に解釈」されるものである。昨今の「共謀罪法案」に良識ある多くの人々が反対しているのは、過去の苦い経験を思い起こすからである。
たとえば、明治33(1900)年に制定された「治安警察法」もそうであった。この法律は、「帝国憲法」第二九条で、一応は認められていた「言論の自由」、「出版の自由」、「表現の自由」、「集会の自由」、「結社の自由」を、実質的に否認するために使用された法律であった。
この法律の権力者による恣意的な解釈によって、「労働三権」の実現は阻まれた。権力側にそれを許したのは、同法第一七条の次の条文であった。
「以下の各号(注、第一号は「団結」、第二号は「同盟罷業」、第三号は「強要」)の目的を達成するために、他人に対して暴行、脅迫、公然たる誹毀、または、第二号の目的のために、他人を誘惑したり、先導したりすることを禁じる」(現代文に直している)。
つまり、「団結権」も、「同盟罷業権」(ストライキ)も、他人を「誹毀」(ひき=誹謗・名誉毀損)し、脅迫行為をした場合には、認められない(罰は、1か月以上、半年以下の禁固刑)というものであった。そして、脅迫や誹毀の事実を認定することのできる主体が明示されていなかったことから、権力側は、恣意的に「罪」を認定する権利を握れていた。
「同盟罷業」は「他人を誹毀」する行為として解釈され、罷業に参加した労働組合員は、同法違反者として逮捕される怖れと、結果的に労働組合の消滅につながる脅威にさらされていたのである。

●力関係を熟知していた●
当時の労働運動の指導者たちが、労働者の同盟罷業を避けたいという姿勢を持っていたのは確かである。しかし、それは、彼らが「ダラ幹」であったからではなく、法の縛りを怖れていたのである。組合幹部たちは、労働組合潰しの口実を当局に与えたくなかった。労組と権力側との力関係を熟知していたからこそ、当時の組合指導者たちは、「同盟罷業」に頼らない労働条件改善の方策に目配りしなければならなかったのである。
その意味でも、部分的ではあれ、「団体交渉権」を企業側に認めさせた藤永田造船所の労働組合は、歴史的に大きな足跡を残したと言える。
●活動家を輩出した闘争●
当時の労働運動の指導者であった片山潜(かたやま・せん、1859~1933年)による「日本に於ける労働」という演説(1899年)がある。その中で彼は語った(要約)。
吾々の組合は今日まで一度も同盟罷工(罷業)をしていない。その必要性は確かにある。内部からそれを決行しようという強い要請も出た。しかし、執行部には資本家と労組との間の衝突を避けねばならない事情があった
(岸本英太郎編『明治社会運動思想』(上)青木文庫、1955年、99頁)。
このような苦しい制約条件の下で、労組を認知させた藤永田造船所の労働者の闘いは、神戸の「川崎・三菱造船所争議」の模範となり、賀川豊彦(かがわ・とよひこ、1880~1960年、川口における大阪労働学校の創設者)という多才な活動家を生みだしたのである。
【 くさり6月号より 】